「美しさ」と「醜さ」の両極端を極めたい──。ホラー漫画家・伊藤潤二先生×"顔面漫画"のいくらさん
日本で一番"歯を描くのがうまい"ホラー漫画家

── 伊藤先生が以前インタビューで、幼少期お姉さまが持っていた楳図かずお先生の漫画を読んでホラー漫画に目覚めたとおっしゃっているのを拝見したのですが、具体的に影響を受けた作品はあるんですか?

楳図先生の作品のなかでは、一話読み切りのものや短編集から強く影響を受けていますね。みやこ高校・新聞部の面々が毎回さまざまな化物に襲われる『恐怖』という作品はとくに印象に残っています。

読み切りや短編は、毎回違う趣向で楽しめるから好きなんですよ。自分の作品も、長編のものはあまりなくて。それは、自分がちょっと飽きっぽいという理由もあるんですが(笑)
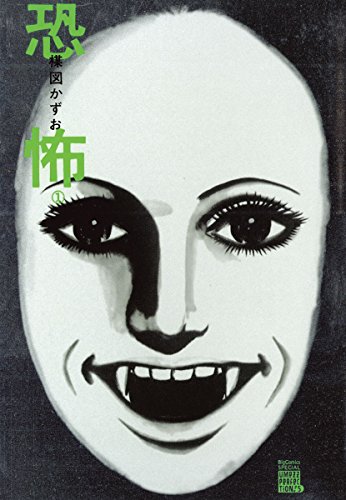
▲ 楳図かずお『恐怖』小学館(2006年)
── 楳図先生の作品も伊藤先生の作品も、短い話のなかに世界観がギュッと凝縮されていて読みごたえがありますよね。ほかに、子どものころ影響を受けたものはありますか?

活字はあまり得意じゃないんですが、中岡俊哉先生の実話系怪談本はよく読んでいましたね。子どものころはとにかく怪獣、幽霊、空飛ぶ円盤が大好きで。そういえば、円盤探知機を作ろうと思ったこともありましたね。

ええ、すごい!


『空飛ぶ円盤ミステリー』っていう本の巻末に円盤探知機のつくり方が載っていたんですよ。磁石を使うんですけど、空飛ぶ円盤が近づくと強力な磁場が発生してブザーがなるという仕組み。ただ、自分で金属の棒を磁石にこすりつけて、細い磁石をつくらなくちゃいけなくて。そこで挫折してしまいました。
── 怪奇的なものの存在は信じていらっしゃったんですね。

日曜の午後は、縁側に出て「円盤出てこないかな」とよく空を眺めていましたね。ただ、あるとき新聞記事で「地球とほかの惑星はものすごく離れているから、なんらかの生命体が宇宙船に乗ってやってくるということは、時間がかかりすぎて、現実にはあり得ない」というのを読んで。なんだか妙に納得してしまって、それから信じられなくなっちゃったんですけど。


私も子どものころは不思議なものの存在を信じてましたけど、自分に見えるわけじゃないのでいまはなんとも言えないですよね。
── ということは、子どものころからホラー漫画家になろうと思っていたんですか?

いえ、漫画家になんかなれるわけないと思っていたので。進路を決めるころには、歯科技工士(※)を目指していたんです。『富江』の第一作目を描いたときは、実際に歯科技工士として働いていました。
※ 歯科技工士:入れ歯、差し歯、矯正器具といった歯科治療に関わる器具の製作や修理を行う仕事
── そうなんですね! 歯科技工士としての経験で、なにか漫画に活かしていることはありますか?

うーん、ペン先を自分の使いやすいように加工できることくらいかな。記憶はすごく鮮明にのこっているんですけどね。

でも、やっぱり歯の表現はすばらしいと思います。こんな風に(とご自身が着ているTシャツのプリントを示しながら)奥歯まで緻密に描かれていて……。

▲ いくらさんが着用しているTシャツには、『双一の勝手な呪い』に登場する双一の釘をくわえた歯の絵がプリントされていました

たしかに漫画家でここまで歯がうまく描けるひとはいないかもしれませんね。ただ、双一の歯はすこしきれいに書きすぎたなと思ってるんです。乱杭歯(らんぐいば)の方がよかったかなと。
── そこから、少女向けホラー漫画雑誌・月刊ハロウィンの「楳図かずお賞」に『富江』の第一作目を送ったことで漫画家の道に進まれたわけですが、『富江』はもともと「こういうものが描きたい!」という構想があったんですか?

いえ、ネタは仕事中に歯を作りながら考えていました。とにかく「楳図先生に見てもらいたい!」という気持ちが強くて。それまで趣味でちょこちょこ漫画を描いてはいたんですが、きちんと仕上げたことがなくて。『富江』がペン入れをした最初の作品です。
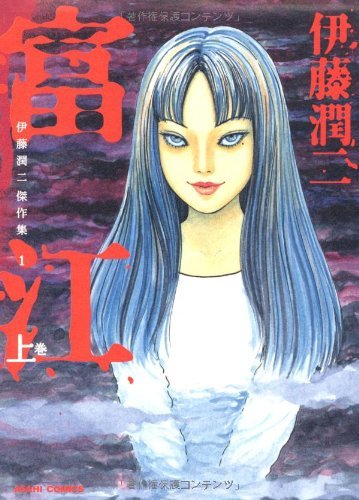
▲ 伊藤潤二『伊藤潤二傑作集1 富江 上』朝日新聞出版(2011年)

はじめは、つけペンがうまく使えなくて製図ペンを使って描いていました。しかも、紙は普通の画用紙。消しゴムを使うと毛羽立つし、インクをつけるとすぐ滲むんですけど。その独特なタッチが『富江』にはすごく合っていた気がします。ただ今はもう、表現できないですね。


たしかに『富江』シリーズの初期の作品は、今とはまた違った雰囲気で独特な魅力がある気がします。初期のものも最近のものも、どちらも好きということに変わりはないんですけどね。
